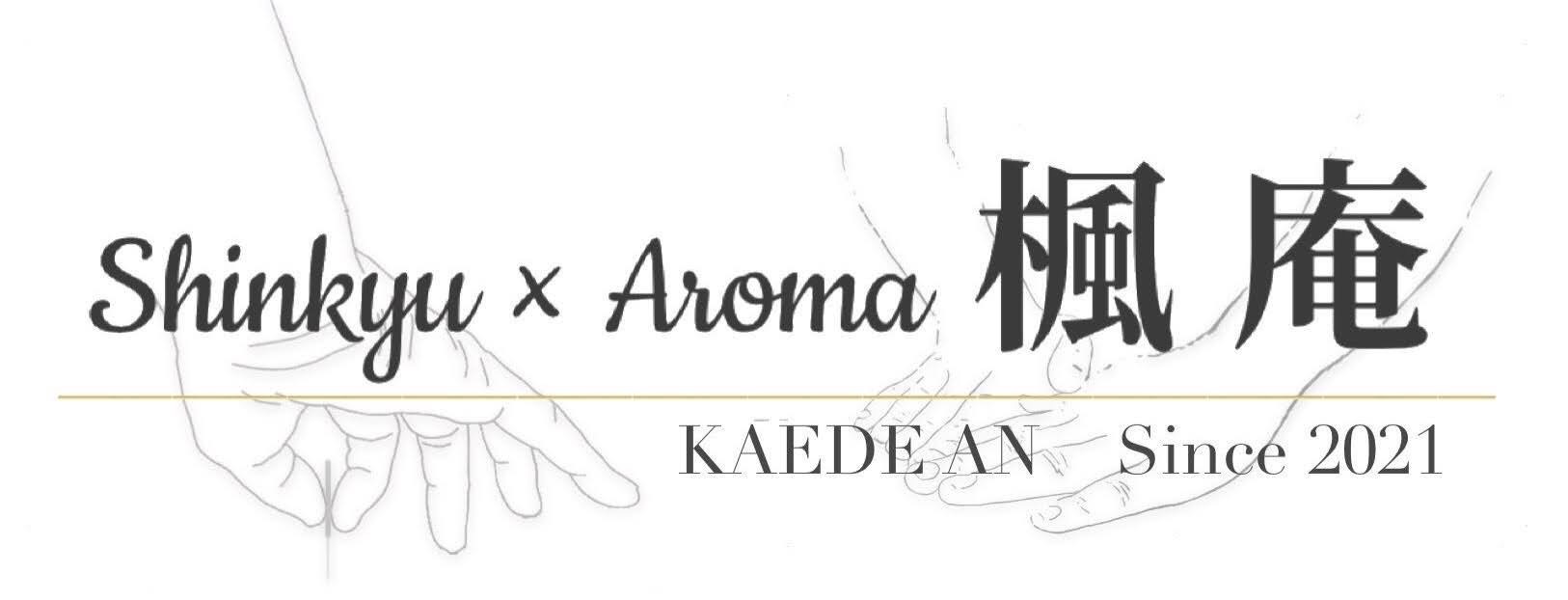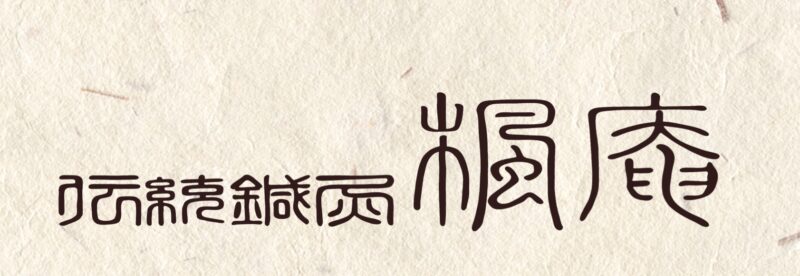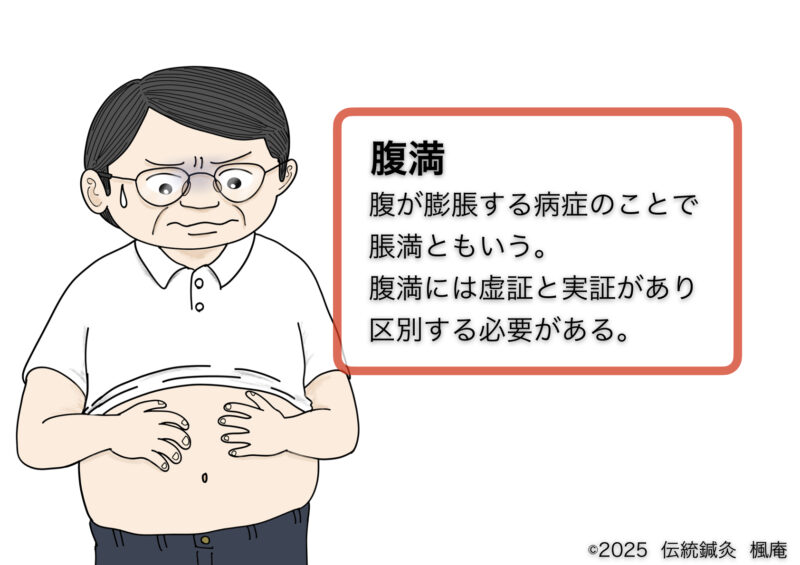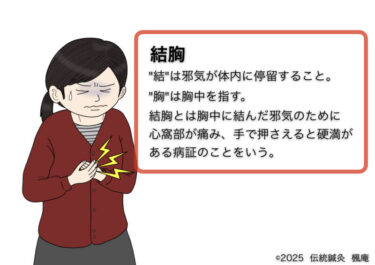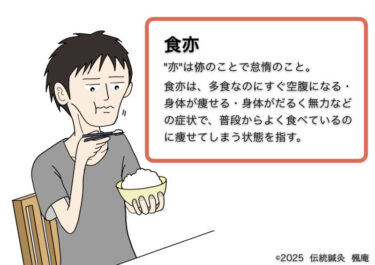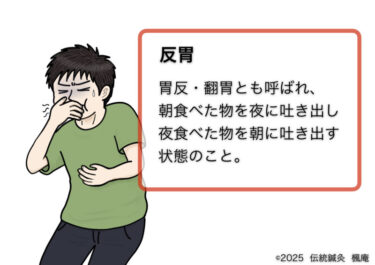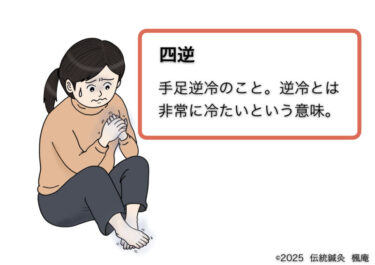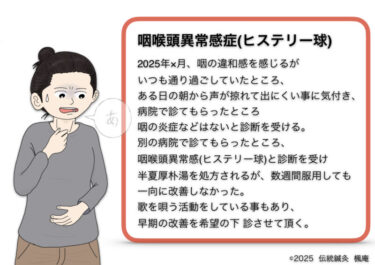腹が膨張する病証のことで
脹満ともいう。
腹滿不減,減不足言,
當下之,宜大承氣湯。
(漢·張機《傷寒論·辨陽明病脈證並治》)
訳:
腹満にして減ぜず、減ずるも言うに足らず、
(漢・張機『傷寒論・辨陽明病脈証並治』)
脹病當先分髒脹、腑脹、虛脹、
實脹,有水無水等因,寒涼溫熱,
攻補消利,方有把握。
(清·余聽鴻《余聽鴻醫案·虛脹》)
訳:
脹病はまず臓脹、腑脹、虚脹、
実脹、水の有無などの原因を分け、
寒涼温熱、攻補消利を把握して
初めて方策がある。
(清・余聴鴻『余聴鴻医案・虚脹』)
心氣太過,土氣亦有餘,故胃乃作
脹而反厚,不能納受水谷,
宜用清火收斂,如芩連,烏梅之類。
今人不識此證,以為飲食不進者,
多是胃氣已弱,仍用參術等類,
則胃益增,飲食反減,
愈補愈脹,病終不愈矣。
(明·馬元台《素問注證發微·卷一》)
訳:
心気太過、土気もまた余りあり、
故に胃は脹れて却って厚くなり、
水穀を納受すること能わず、
宜しく清火収斂を用うべし、
芩連、烏梅の類のごとし。
今人この証を識らず、飲食進まざる者は、
多くは胃気既に弱しと為し、
依然として参術等を用うれば、
胃は益々増し、飲食は却って減じ、
補えば補うほど脹れ、病は終に癒えず。
(明・馬元台『素問注証発微・巻一』)
凡腹脹滿而漫腫虛大者,屬氣滯;
腫硬光亮者,為水結 ①;少腹濡腫而痛,
有青紫筋膜絆於腹皮者,為瘀積也;
腹滿不減,按之痛者為實,承氣湯下之;
腹滿時減,按之不痛為虛,理中湯溫之;
病人自言腹滿,他人按之不滿,
此屬陰證,切不可攻,攻之必死,四逆湯溫之。
(清·張璐《傷寒緒論·卷下腹滿》)
[注釋]①水結:水濕之邪結滯於
訳:
凡そ腹脹満にして
漫腫虚大なる者は気滞に属す;
腫硬光亮なる者は、水結①と為す;
少腹濡腫にして痛み、青紫の筋膜が
腹皮に絆われる者あるは、瘀積なり;
腹満にして減ぜず、
按じて痛む者は実と為し、承気湯にて下す;
腹満にして時に減じ、
按じて痛まざる者は虚と為し、
病人自ら腹満といい、他人按じて満たざるは、
これ陰証に属す、決して攻むべからず、
攻むれば必ず死す、
(清・張璐『傷寒緒論・巻下腹満』)
[注釈]①水結:水湿の邪が
内に結滞する、水臌のような病証。
內,如水臌一類的病證。
腹滿不減者為實,當下之;
腹滿時減者,為里虛,當溫之。
(清·田宗漢《醫寄伏陰論·卷下》)
訳:
腹満にして減ぜざる者は実と為し、
直ちにこれを下すべし;
裏虚と為し、直ちにこれを温むべし。
(清・田宗漢『医寄伏陰論・巻下』)
脹,謂脹於外。滿,謂滿於中。
排髒府而廓胸脅,急皮膚而露經脈,
臍凸腰圓,鼓之如鼓,胸腹之疾也。
亦有脹及於頭面四肢者,與水腫大同小異,
而此則無水耳。
大抵飲食不節,起居失宜,
房室過勞,憂思無極,
久久皆足以耗其守陰,
衰其陽運,致氣壅滯留中,
而脹滿之疾漸起矣。
故實者少,虛者多。熱者少,寒者多。
成於他髒者少,成於脾胃者多。
(明·王紹隆《醫燈續焰·脹滿脈證》)
訳:
脹は、外に脹れるを謂う。
満は、中に満ちるを謂う。
臓腑を排し胸脇を廓げ、
皮膚を急にし経脈を露わし、
臍凸腰円、鼓のごとく鼓し、胸腹の疾なり。
また頭面四肢に脹及ぶ者あり、
水腫と大同小異なるも、これには水なし。
大抵飲食を不節して不摂生をし、
房事過多や過労、深く思い悩み、
久しく皆その守陰を耗し、
その陽運を衰えさせ、
気をして中に壅滞せしめ、
脹満の疾漸く起こる。
故に実なる者少なく、虚なる者多し。
熱なる者少なく、
他の臓に成る者少なく、
脾胃に成る者多し。
(明・王紹隆『医灯続焰・脹満脈証』)
少腹滿,必有物聚而為之滿。
在上而滿者,氣也;在下而滿者,物也。
物者溺與血也。少腹硬,小便自利,
其人如狂者,血證也。當出不出,積而為滿。
(明·劉純《傷寒治例·少腹滿》)
訳:
少腹満、必ず物聚まりてこれを満たす。
上にあって満つる者は、気なり;
下にあって満つる者は、物なり。
物とは溺と血なり。少腹硬く、小便自利し、
その人狂のごとき者は、血証なり。
当に出ずべきもの出でず、
(明・劉純『傷寒治例・少腹満』)
蓋中滿之疾,原是氣虛而成,不補
其虛,何以解?
(清·陳士鐸《石室秘錄·塞治法》)
訳:
蓋し中満の疾は、元来気虚にして成る、
その虚を補わずして、何をもって解せん?
(清・陳士鐸『石室秘録・塞治法』)
脹滿之證,多是脾胃素弱,或病後
失調,外為風寒暑濕之氣所侵,
內為憂思七情之氣所傷,
及過食生冷飲漿之類,並傷脾胃,
以致五臟傳克,陰陽之氣不得升降,
痰飲結聚中焦,遂成脹滿之疾。
(明·熊宗立《名方類證醫書大全·卷十四·脹滿》)
訳:
脹満の証は、多くは脾胃素弱、或いは病後
失調、外は風寒暑湿の気に侵され、内は憂
思七情の気に傷られ、及び生冷飲漿を過食
する類、並びに脾胃を傷つけ、五臓をして伝克せしめ、陰陽
の気は升降することを得ず、痰飲は中焦に結聚し、遂に脹
満の疾を成す。
(明・熊宗立『名方類証医書大全・巻十四・脹満』)
少腹滿者,有物聚也。蓋身半以上
同天之陽,身半以下同地之陰。
清陽出上竅,陰出下,故在上滿者氣也,
在下滿者物也。物者與血爾。
邪結下焦則津液不通,血氣不行,
或溺或血流滯而脹滿也。
(明·王肯堂《證治準繩·傷寒·少腹滿》)
訳:
少腹満なる者は、物聚まるなり。蓋し身半以上は
天の陽に同じく、身半以下は地の陰に同じ。
清陽は上竅より出で、陰は下より出づ、
下にあって満つる者は物なり。物とは血と爾。
邪が下焦に結滞すれば津液は通ぜず、血気は行かず、
或いは溺或いは血が流滞して脹満となる。
(明・王肯堂『証治準繩・傷寒・少腹満』)
"結"は邪気が体内に停留すること。"胸"は胸中を指す。結胸とは胸中に結んだ邪気のために心窩部が痛み、手で押さえると硬満がある病証のことをいう。結胸有輕重,立方有大小。從心下至小腹,按之石硬而痛不可近者,[…]
食亦(しょくえき)"亦"は㑊のことで怠惰のこと。食亦は、多食なのにすぐ空腹になる・身体が痩せる・身体がだるく無力などの症状で、普段からよく食べているのに痩せてしまう状態を指す。食亦者、飲食不為肌膚、言雖食[…]
胃反・翻胃とも呼ばれ、朝食べた物を夜に吐き出し、夜食べた物を朝に吐き出す病態を反胃という。其食虽可下,良久复出,病在幽门,名日反胃,此属中焦;其或朝食暮吐,暮食朝吐,所出完谷,小便赤,大便硬,或如羊矢[…]
四逆の”四”は両手両足のことで”逆”は逆冷(非常に冷たい状態)("逆冷"よりも酷い状態を"厥冷"という)であることから手足がキンキンに冷えた状態を四逆という。手足の冷えではあるが、・陽虚・寒邪・熱邪・気滞・瘀[…]