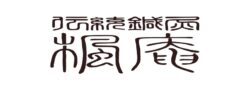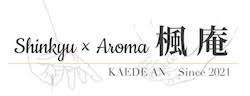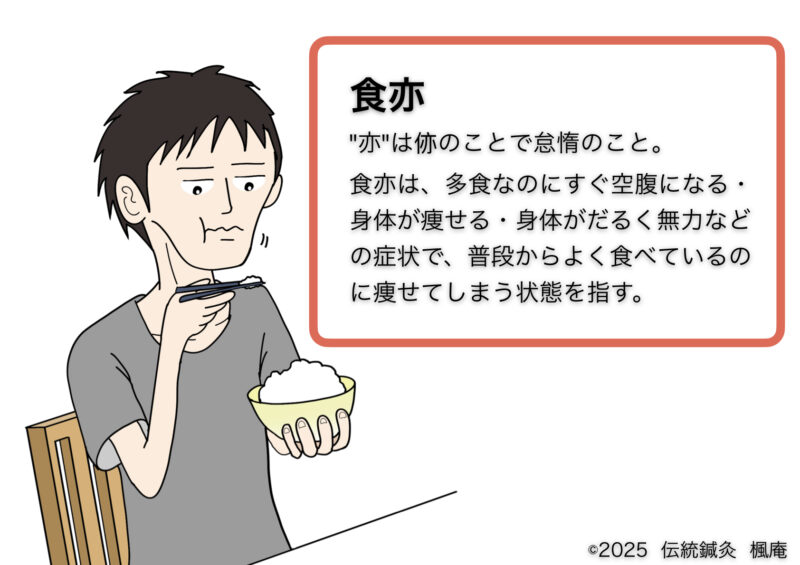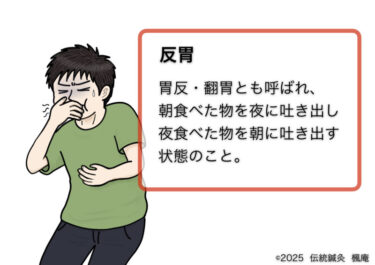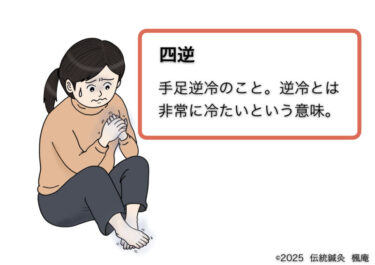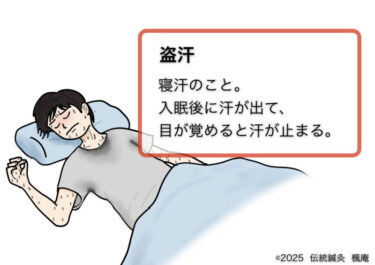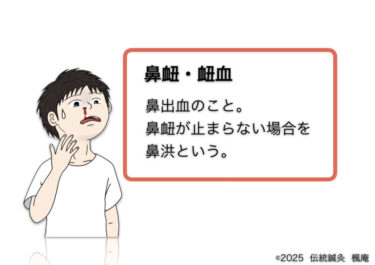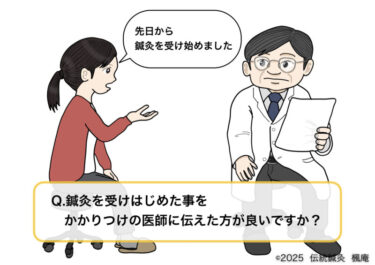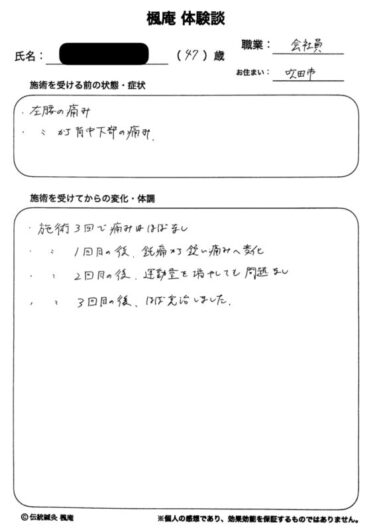食亦(しょくえき)
“亦”は㑊のことで怠惰のこと。
食亦は、多食なのにすぐ空腹になる・
身体が痩せる・身体がだるく無力
などの症状で、普段からよく食べているのに
痩せてしまう状態を指す。
食亦者、飲食不為肌膚、
言雖食猶若飢也。
蓋大腸移熱於胃、善食而瘦、謂之食亦。
夫胃為水谷之海、所以化氣味而為營衛者也。
若乃胃受熱邪消爍、谷氣不能變化精血、
故善食而瘦也。
又、胃移熱於膽、亦名食亦。
以膽為陽木、熱氣乘之則土而消谷。
(清・陳念祖《醫學金針・卷三・食亦》)
若乃胃受熱邪消爍、谷氣不能變化精血、
故善食而瘦也。
又、胃移熱於膽、亦名食亦。
以膽為陽木、熱氣乘之則土而消谷。
(清・陳念祖《醫學金針・卷三・食亦》)
訳:
食亦とは飲食が肌膚のためにならず、
食亦とは飲食が肌膚のためにならず、
大腸から胃に熱を移し、
もし胃が熱邪に侵され、
また、
胆は陽木であり、熱気はこれに乗じて
土となり穀を消す。
(清・陳念祖 『医学金針・巻三・食亦』)
其善食而瘦者、名曰食亦。
(金・張從正《儒門事親・三消之說當從火斷》)
訳:
よく食べるのに痩せる者を食亦という。
(金・ 張従正『儒門事親・三消之説当従火断』)
よく食べるのに痩せる者を食亦という。
(金・ 張従正『儒門事親・三消之説当従火断』)
有善食而瘦者、胃伏火邪於氣分、
則能食、脾虛則肌肉削、即食亦也。
(金・李杲《脾胃論・脾胃勝衰論》)
訳:
よく食べるのに痩せる者がいるのは、
よく食べられるが、
肌肉が削げ落ちる、すなわち食亦である。
(
よく食べるのに痩せる者がいるのは、
よく食べられるが、
肌肉が削げ落ちる、すなわち食亦である。
(
大腸移熱於胃、善食而瘦、人謂之食亦。
(《黃帝內經素問・氣闕論》)
訳:
大腸が胃に熱を移し、
よく食べるのに痩せるのを、
(『黄帝内経素問・気厥論』)
胃反・翻胃とも呼ばれ、朝食べた物を夜に吐き出し、夜食べた物を朝に吐き出す病態を反胃という。其食虽可下,良久复出,病在幽门,名日反胃,此属中焦;其或朝食暮吐,暮食朝吐,所出完谷,小便赤,大便硬,或如羊矢[…]関連記事
四逆の”四”は両手両足のことで”逆”は逆冷(非常に冷たい状態)("逆冷"よりも酷い状態を"厥冷"という)であることから手足がキンキンに冷えた状態を四逆という。手足の冷えではあるが、・陽虚・寒邪・熱邪・気滞・瘀[…]関連記事
盗汗(とうかん)は、盗賊がこっそりと物を盗むように入眠後にこっそり汗が出ることから盗汗といわれている。主に、陰虚内熱からくる盗汗をよく診ますが、内傷病か外感病かを区別する必要があり内傷病は虚証に多く、外感[…]関連記事
鼻血のこと。臨床的には表証と裏証とある。・表証風寒に侵された後鼻出血で寛解することもある。風熱でも鼻出血することはあるが、寒証・裏証ともに少量の出血である。・裏証飲酒や辛辣の物を過食して出る鼻出血[…]関連記事